当コーナーは、当協会前理事である渡辺好明氏が学長を務める
「新潟食料農業大学」のコラムを掲載しています。
【番外編⑨】食、農、地域のあれこれ
今回は、英語になった日本語、とくに食べもの英語、
そして、アメリカと日本での学校給食への考え方の違いについて触れる。
14 英語になった日本語
母校の藤原 保明 筑波大学名誉教授の公開講座(2015年6月)のサワリである。
オックスフォード英語辞典に登場する「英語になった日本語」は、
600年で177語とか。
例えば、「ハラキリ」「ゲイシャ」「ツナミ」などは相当に古い。
食べものでは、「サケ(sake)酒」、「ソイ(soy)醤油」は1680年代には早くも登場
「ミソ(miso)味噌」は1720年代に登場とこちらも相当に古い。
これらの語数はいまなお増加しつつあり、最近もっとも新しいものとしては、
「ヒキコモリ」「カワイイ」「ケイタイ」を挙げておられた。
さて、最近10年での新規参入を食品、料理の分野に限れば
「ベントウ」「カイセキ」「タタキ」「トロ」ときて
極みは、「ワギュー」と「ウマーミ」である。
和食文化がかなり国際化を見せている証左ではなかろうか。
ちなみに、「スシ」は1890年代、「スキヤキ」「テンプラ」は1920年代、
「シャブシャブ」は、1960~85年代に搭載したと解説されていた。
(続・風に吹かれて 2015年9月号)
15 地域の食材を学校給食に
給食においては各地で「センター方式」か「自校調理方式」かと長らく議論が続いているが、
地域教育の観点からは、後者が望ましい。
大量の同一規格材料がそろわないとか、児童たちの平等性が保てないという議論は、
現在の食水準の中では、相も変わらぬ「完全栄養給食」を求める、ちょっと時代遅れの考え方ではないか。
今日のアメリカでは、“Farm to School Program”と称する運動が盛んで、
ローカル・フードを積極的に学校給食に利用する取組みが増えている。
全米の40を超える州の9000もの学校で実践されている。
日本でも、さいたま市の全小中学校(56校)は、「自校調理方式」に切り替え、
食材でも3割を県産の農産物で賄うことにしたという。
児童・生徒が自分でご飯を炊く、学校近くの生産者の農産物を使う、
地域に伝わる料理を教えてもらいながら自分たちで作って体験するということが真の食育である。
(続・風に吹かれて 2016年12月号)
.............................................................................................................................
【番外編⑧】食、農、地域のあれこれ
今回は、ふたたび水の制御の話、そして、ロシアがウクライナから自国への編入を強行した
クリミアについてのエピソードに触れる。
12 「低水工事」の方法は使えないか
水制御の手法として、近代の工事の主流は、洪水(高水)を堤防によって
「完全に押し込める」ところにあるが、古くはあらかじめ溢水、洪水などは織り込んで(溢れさせ)
水防林などで洪水の力を弱める、なだめる方式=低水工事、これが明治中期までの主流であった。
(富山和子2010年)
いうなれば、controlするのではなく、manageするということなのか。
岐阜の輪中、渡良瀬の遊水地、各地にみられる舟形防水林などもこれに類する。
しかし、「一定の被害が出ることを前提とする」ものだから、現段階の日本では、まだ難しいかもしれない。
ついでに余談を一つ。互いに自己主張をして譲らず延々と言い争う「水掛け論」
自分の都合のいいように言ったり、したりする「我田引水」
これらはいずれも、江戸時代の農民たちの水資源争いから生じた言葉で
なんとしても自分の田にだけは水を入れようとする姿勢から起こったといわれる。(渡辺尚志)
(続・風に吹かれて 2014年6月号)
13 クリミアの稲作
ロシアが実力で自国の領土に編入したクリミア、ウクライナ・ロシア紛争は農業にも影響を及ぼしている。
マスコミによれば、ウクライナが農業用水の供給を止めたため稲作ができず
やむを得ずトウモロコシ栽培に切り替えたが、収入は減るとの報道があった。
うかつにも「ウクライナで稲作」とは初耳であった。
エジプト、イタリア、スペインなどは知られているが、実は当地も年間約6万トン(新潟の1/10)、
単収は500kg/10a(モミベース)のコメ産地だという。
アメリカ農務省の調査能力はすごい。(続・風に吹かれて 2014年8月号)
.............................................................................................................................
【番外編⑦】食、農、地域のあれこれ
今回は「七草がゆ」を取り上げ、あわせて樹木の落ち葉についての優しい言葉を紹介する。
10 七草がゆ
1月7日は「七草がゆ」、正月料理や連日の飲酒で疲れた胃袋を休ませるため
消化のよい七草がゆを食べる習慣が生れたともいわれている。
もっとも、最近では、<草摘み>などをする必要はなく、スーパーなどでもよく売られている
「七草がゆ・材料7種セット」などをおかゆに混ぜて加熱するだけでよい便利さだ。
ずいぶんと昔のことになるが、母親が七草を刻むときに
<七草なずな、唐土の鳥が日本の土地にわたらぬ先に>といいながら、
まな板をトントン調子よく叩いていた記憶がある。
これを、佐渡育ちの家内の母親に話したところ、「東京でもそうなの?」といわれたことを思い出す。
全国的な行事だったのだ。
古くは、6世紀頃の中国(梁)で、人の爪を食らうという鬼鳥(鬼車鳥)を防ぐため
正月7日に門戸、床を叩く習慣で、正しくは、7×7の49回たたくのだそうである。
なお、一般的にいわれる歌詞に「唐土の鳥と<日本の鳥と>」があるが
これは、<土地>が<鳥>にトリ違えられたのであろう。
(続・風に吹かれて 2014年2月号)
11 常盤木(ときわぎ)落ち葉
常緑樹のシイ、カシ、クスなどは、新緑の季節に新しい葉が盛んに育ち
古い葉が次々に枯れ落ちる。若い世代に立場を譲っているようであらる。
これと関連して、「ユズリハ(譲り葉)」(樹木の名前)(淡路の山脈の名称)ともいう。
(風に吹かれて 2013年3月号)
.............................................................................................................................
【番外編⑥】食、農、地域のあれこれ
ヒンズーとイスラムなど日本の食が海外に進出するには
いずれは、ハラルの認証など相手国の宗教事情も知らなければならない時代になった。
今回は、ヒンズーと乳牛、役牛、肉牛との関係について解説したい。
9 「聖なる牛」とは?
ある業界紙(米麦日報)が報じた「インドの畜産事情」なる講演からである。
そのまた一部を要約すると、「インド畜産の主力は“水牛”で、メスは、乳用とされた後に肉用に処分される。
オスは、乳が出ないし、持久力もないので役牛にはならず、誕生後2週~1年で、肉用に処分される。
“乳牛”(在来種、ジャージー、ホルスタイン)の場合
オスは、①在来種では運搬、農耕用を経て肉処分、②ジャージー、ホルスタインは肉用に直行となる。
水牛は、そもそも牛の範疇に入らないので、これらを考えると
インドでは、神様=聖なる牛」とは、すなわち『乳用種のメス』だけということになり
乳が出なくなった<老後>も、道の草をはみながら悠悠自適なのである
インドの人口のうち81%、9.7億人はヒンズー教だから牛は食べにくく、
抵抗感がないのはトリ肉だろうとも語っていたが、イスラム教徒も13%、
1.6億人なので牛肉への絶対需要量は相当なものと推測する。
タマゴも同様で、人口大国インドには、やりようによっては、膨大な需要が待っているといえるだろう。
(風に吹かれて 2013年11月号)
.............................................................................................................................
【番外編⑤】食、農、地域のあれこれ
前号に引き続き、水の制御手法としての「コンクリート・マットレス」とちょっと閑話休題で
「モグラとゴキブリ」の話をしてみます。
7 コンクリート・マットレス
北海道大学の前身である「札幌農学校」の岡崎文吉が1902年に発明した護岸技術、
この改良型は、いまでもアメリカのミシシッピ川で現地生産され、利用されている。
その基本は、「いかなる大河でも水は蛇行する。従って、水流の当たる
箇所のみの崩壊を防ぐマット(=長方形のコンクリートを針金で繋いでスダレ状にしたもの)を
垂らすのが有効な対応策である」というところにある。
これによって、崩壊を防ぎ、同時に、水深(=水路)も確保できる。
自然、水に逆らわず、共生こそが大事だというのである。
この考え方を英語に映すと、支配する“Control”ではなく
上手に折り合いをつける“Manage”に当たるのかもしれない。(風に吹かれて 2013年3月号)
8 モグラとゴキブリ
・モグラ
わが国は、長らく「アズマモグラ」の天下であった。太平洋戦争後のこと、
南洋種の「コウベモグラ」が九州に上陸して東征、瞬く間に勢力を伸ばした。
富士川の線まで進出して東西の均衡がしばしの間は保たれていた。
その理由は、コウベモグラは、高冷地、溶岩地には比較的弱いのだと説明されていたのだが、
なんと、富士山を北側から迂回して、関東地方に達したようである。
ちなみに、コウベモグラとはいっても、たまたま発見地が「神戸」だっただけで、もともとは南洋種なのである。
・ゴキブリ
これも種類は多い。象徴的なのは、「クロゴキブリ」と「チャバネゴキブリ」である。
比較的寒さに弱いチャバネゴキブリだったが、耐寒性能のよい家屋の普及、道路、鉄道、橋、トンネルの発達で
自動車、列車に便乗して東進したと考えられている。
(風に吹かれて 2013年1月号)
.............................................................................................................................

【番外編④】食、農、地域のあれこれ
農業生産に不可欠な要素は、土地(農地)、水、人(担い手)、技術だといわれるが
そのうちの「水」=用水のエピソードを取り上げる。
なお、第28回のコラムにおいて、新潟の疏水(疏水百選)を紹介しているので
こちらもぜひ読み返してほしい。
6 木曽山用水
「木曽山用水」は、木曽「川」用水ではない。
つまり、この用水は、1969年の大改修までは、流れが、実際に、山である「権平峠」を越えていた。
長野県・伊奈の南箕輪村「上戸」「中条」集落は、天竜川の支流「小沢川」の下流に位置し
一見、水は豊富そうに思えるが<旧松本藩の飛び地>ということもあって「水利権」がなかった。
アワ、ヒエしか取れない土地にとって、自前の水の導入は長年の悲願であった。
江戸から明治にかけての再三の請願の効果と新たな水利用の手法が編み出されたことから、
問題は一気に解決する。
木曽側の「奈良井川」(信濃川水系)の水を分水し
これをほぼ等高線沿いに流して標高1,522mの権平峠を越えさせ、
伊那側の「小沢川」(天竜川水系)に落水・流入をさせる。
下流の2つの集落は、その落水・流入された分と同量の水を取水し利用できるという
「玉突き取水法」を考案したのである。これに
よって2つの集落では、水田、稲作が可能となり、やがて、恵み豊かな地域に変わったのだといわれている。
本来なら、日本海に注ぐ奈良井川の水の一部を、峠を越え、天竜川を経由して
太平洋に注がせる一大工事であった。
「玉突きは同量の水」という大前提だから、厳密な計測・確認は、いまでも慣例として行われている。
取水口である「水枡」からピンポン玉を流し流速を確認、
流量をはじき出す伝統行事は、トンネル、パイプラインとなった今日も引き継がれていると聞く。
(風に吹かれて 2012年10月号)
.............................................................................................................................
【番外編③】食、農、地域のあれこれ
エデイブル・フラワーとミツバチを取り上げる。
ちなみに、日本人が好む海藻類は、「エデイブル・シーウイード」という。
もう一つは、野菜や果物を結実させる「交配機能」を果たすミツバチで、いずれNAFUでも導入したい。
4 エデイブル・フラワー(食べられる花)
新潟の「食用菊」は有名で、刺身のつまはもちろんかなりの量を「酢の物」にして食べるが
ここではちょっと毛色の変わったエデイブル・フラワーを紹介する。
まずは、信州安曇野の「宗徳寺」である。
寺は法事や人の寄り合いも多く、常にお茶うけの漬物が欠かせない。
ある日のこと、鮮やかなピンクの酢漬けを出されて
「当ててみてください。ヒントは目の前、庭にあります」と言われた。
目を中庭に移すと、そこには、見事な石楠花(アズマシャクナゲ)がある。
新しい花から雄しべ、雌しべを外し、ごく軽く湯通ししてから酢漬けにすると、
酢の力でピンク色がよみがえって、目の前の美しい漬物になるというのだ。
つぎに、埼玉・羽生の「全龍寺」では、「お土産に藤の花でもいかがですか?とてもおいしいですよ」と問われ、
ビックリしたことを思い出す。
シャクナゲの花と同様に、新花をこそいで、おひたし、酢漬け、天ぷらにすればおいしい。
とくに香りはすばらしいという。「クローバーもタンポポもみな食べられます」と説明され
食べものは「買う」ばかりではない、経済が豊かになると、
かえって、季節を感じる感覚が貧困になるのをどうすればいいか、考えさせられた。
(日本橋人形町だより 2009年5月号)
5 リンゴの花とミツバチ
白馬村の古くからの養蜂家によれば、
「リンゴの花は美しいが、消毒薬も大量に使われる。
ミツバチは繊細な生き物であるので、この時期には外に出さない。」
岩手の有名な養蜂家の藤原さんも同じ指摘をする。
こちらは、「稲に使われるネオニコチノイドが最も危険だ。
そもそも稲に使わなければならない必然性はないし、
そうした薬品は、最も弱い生物であるミツバチにも害がないレベルでなければならない」というが、
もっともだと思う。
ハチは、蜜を採取するばかりでなく、温室内の農作物の交配に不可欠なものである。
それがダメージを受けたのでは元も子もないのだ。
残念なことに、これは、人間への警告かもしれない。
(風に吹かれて 2012年5月号)
.............................................................................................................................
【番外編②】食、農、地域のあれこれ
今回は、地域の繁栄に不可欠な農村風景についてである。
南ドイツのバイエルンは世界屈指の美しい景観を持つが
これは地域の人々の「景観は財産」という意識と努力によって維持されている。
3 バイエルンへの道 – 美しい農村風景
ミュンヘン中央駅30番ホームを列車で出てから、ものの30分も経つと平坦な農地が展開し始め、
冬小麦の刈取り跡、トウモロコシ、牧草、休閑地が整然と分けられ、農地は完全利用されている。
平地林は、きちんと枝打ちされ、間伐材とともに、燃料用の薪として積み上げられている。
ソーラー発電、風力発電も景観を妨げない形でなじむ。
温室、ハウスも見かけない。
村の集落は、農家がまとめられ、赤い屋根、白い壁で、高さも2階+屋根裏に統一されている。
いくつかの集落に一つは教会の尖塔が見える。
村そのものの存在が観光価値を持つ地域資源で、
実際にも列車に自転車を積み込んできて、駅のホームからそのまま農道へと走り出す
サイクリングの人々も多数見かける。
地域内に青少年がリュックを背負って歩き回る風景がしばしば見られるのは、
ここが美しいからだけではなく、ワンダーフォーゲル発祥の地であることとも関連しているかもしれない。
列車が1時間を過ぎて速度を落とし、少し丘陵地帯に入ると、農地の風景も変わる。
牧草一色になって、乳牛が増えてくる。
目を凝らして見ても、穀物を多く消費するホルスタインはわずかで、牧草で高脂肪の乳を出して、
肉用にもなる牛 =「スイス・ブラウン」が圧倒的だ。
2時間後、列車は、オーストリア(チロル)との国境、バイエルン・アルプス麓の町「フュッセン」に滑り込む。
改めて感じるのは、日本の場合、街づくりでフランスに負け
村づくりではドイツに遙かに引き離されているということであった。
(日本橋人形町だより 2008年8月号)
.............................................................................................................................

【第38回】カツオの回遊と水産物の産地市場
江戸の初ガツオ
“目に青葉 山ほととぎす 初鰹” 旧暦の4月ごろ(いまの5月ごろ)に、伊豆沖にやってきます。
獲られたカツオは小田原、鎌倉、三崎湊などに陸揚げされて馬や舟で江戸へ急送されます。
ムカデのように櫓(ろ)を出した「八丁櫓(はっちょうろ)」の快速船(8人で櫓を漕ぐ)に積んで
江戸湾を突っ切って、日本橋魚河岸に向かうのです。
コールドチェーンの整備されていなかった当時は、スピ-ドだけが頼りで
また早ければ早いだけ値も高く、最初のカツオに1尾10万円近い値段がつくこともあったそうです。
カツオの回遊路
日本沿岸のカツオにはいくつかの群があり、主な2群の回遊路は
3月の先島諸島沖(西表島、石垣島)→4月の沖縄、奄美、トカラ諸島→5月の鹿児島沖へ。
別の群は、5月の伊豆諸島沖→6月の房総沖へ、そして、7月には、宮城県の金華山沖、三陸沖
やがて9月には、北海道沖のエサが豊富で黒潮、親潮の境目に達します。
8月ごろからは、エサを十分に食べて南下する個体も多くなり、これが「下り鰹」です。
一般に、痩せたカツオは鰹節に、下り鰹は生食に向くといわれます。
漁港と水産物産地市場
『港町ブルース』(1969年)には数多くの漁港が登場しますが
統計上の水揚げの多いのは焼津、銚子、八戸、境、枕崎あたりベスト5でしょうか。
<伊豆沖と江戸>のような狭いつながりの場合は産直でも済むのですが
いまのように1年間を通じて広くカツオの漁獲を続ける漁船の場合には
魚=漁場の移動に対応しながら、漁獲の都度、最寄りの漁港=「水産物産地市場」に立ち寄って
魚の陸揚げ→販売・入金→船員給与の支払い→燃油、漁具、エサの手当てなどが不可欠になります。
そうでないとつぎの漁場への出港もできません。
この機能・役割を果たしているのが「産地市場」です。
農水産物卸売市場の役割
消費地市場も産地市場も、基本的機能は共通です。
集荷→評価・販売(価値実現)→分荷・配達などですが
加えていまでは金融(必要な費用の用立て)、情報収集・提供などの機能も求められます。
モノ、金、ヒト、情報の集積が市場の優劣を決めるのです。
物流面だけを見て「産地市場はムダ、産地―消費地の直結が望ましい」というのは現実的ではないでしょう。
時代の変化と流通、今後の行方には目が離せません。
.............................................................................................................................
【第43回】納豆の経木、世界の納豆仲間、発酵食品
「納豆シリ-ズ」の第2弾、納豆の販売容器であった「経木」などを取り上げます。
三角形の経木(きょうぎ)
かつての納豆の包装「経木」は「アカマツ」を紙のように、ごく薄く削ってできるそうです。
小泉 武夫さんなどによれば、このアカマツには旨味成分である「アミノ酸」が含まれていますから
経木を通して納豆の味が一層よくなるのだそうです。
なお、ここからは推測ですが、松茸が赤松の根に生えるのもそのせいかもしれません。
納豆の仲間たち
納豆は、日本でだけの食品ではありません。
東南アジアにも広く分布し、とりわけ照葉樹林文化圏と重なるように思えます。
朝鮮半島、中国南部、タイ、ラオス、ミャンマー、インド東北部、ネパ-ルには
似たようなものがあり、なぜか西アフリカにも飛地のように
「ダウダウ、スンダラ」という納豆があるといいます。
糸を引くもの・引かないもの、乾燥しているものと、その種類も多様です。
乾燥の納豆は旅行携帯用にも便利です。確か、有楽町のJALショップで売っていました。
日本の発酵食品は世界一
発酵食品は日本が世界一でしょう。
醤油、味噌、日本酒、酢だけではなく数え切れないほどです。
これに大きな貢献をしているのが、自然界にある麹菌、酵母、乳酸菌などです。
煮た大豆をすりつぶして「味噌玉」にし、空中に吊り下げておくと
味噌麹が付着しておいしい味噌になっていきます。
長野県の北安曇地域では、今でもこのやり方でおいしい味噌が作られています。
大豆につく麹菌、米につく麹菌と相性は異なるようです。
新潟は、日本酒の蔵元がが90もあるように、本来は発酵食品の大産地なのですから
これからは、もっともっと発酵食文化の発信基地になっていいですね。
余談ですが、空中の麹菌や蔵の中に漂う酵母は日本酒の醸造に決定的な役割を果たしていますので
かつて東京・北区の「醸造試験場」が広島に移転したときには
コンテナに空気(=酵母)を入れて移動させたとも報道されていました。
フードコースで、古くとも理に適っている食品の製造を「科学的に」解明しましょう。
.............................................................................................................................
【第42回】納豆の起源と発酵食品
日本は、温暖・湿潤な気候風土のため、<有用な菌類>の宝庫です。
穀物・豆類を煮て塩を加え、空気にさらせば麹菌や酵母が働いて
腐敗は防止しつつ発酵が進み、醤油、味噌、日本酒、酢などが生まれます。
そして、長期の保存も可能になります。
また稲ワラなどに生息する<枯草菌>(納豆菌)はその発酵作用で、納豆を作り出します。
今回のコラムでは発酵食品の中から「納豆」を選び、いつ、どうして誕生したのか
歴史とエピソードに触れてみたいと思います。
弥生時代に生まれた?
納豆(糸引き納豆)は、煮大豆と稲ワラに含まれる「納豆菌」によりできます。
容器代りのワラに入った納豆がいまでも見られます。
それで、稲作が本格化した弥生時代まで起源を遡(さかのぼ)れると想定するのです。
(古文書に登場するのは、平安時代中期)
奥州征伐の戦さで偶然に?
面白い伝説としては「八幡太郎・源義家」が後三年の役の際に
急な戦いが勃発し馬糧だった稲わらに、煮大豆を「一時保管」して
戦いが済んだ後で開けたところ、発酵していた。勇気をふるって食べたところおいしかったというのです。
水戸黄門の納豆は黒大豆?
納豆は茨城・水戸の名物ですが、引退後「西山荘」に住んだ水戸光圀が注文して作らせた納豆は
原料が黒大豆だったということを聞いたことがあります。
しかし、「水戸黄門漫遊記」には、納豆は登場しませんね。
スーパーの棚を見ると<北海道産の小粒黒大豆の納豆>が並んでいることがあります。
稲ワラに入った煮大豆から納豆が生れたことはほぼ分かりましたので
次回は「納豆がなぜ三角形の経木(きょうぎ)=容器に入れて売られていたのか」などを調べてみましょう。
.............................................................................................................................
【第41回】読書のすすめ
今回のコラムでは、ぜひ皆さんに読んでもらいたい3冊(+1冊)の本を取り上げます。
『生物の世界』(今西錦司 講談社文庫)
ダーウインのいわゆる「競争→淘汰」に対して
存在するものにはそれぞれ意味がある「棲み分け」の理論が展開されます。
これらは、環境と生物の関係のみならず、社会構造にも至っています。
1940年の発刊にも拘わらず生態系、食物連鎖、生物多様性などとの関わりは
グローバル化が賑やかな現代にも通じます。
『日本社会の歴史』(網野善彦 岩波新書 上中下)
<日本>の歴史ではありません。日本社会はこれまでの定型的な歴史教科書で学んだ状況と違い
多様な人々、とりわけ女性たちの活躍で進歩してきました。
「百姓」とは農業者のみを意味するのではなくて
多様な職業、商売の人々と考えています。民衆(常民)の日本史ともいうべき書籍です。
また、いまでは離島・僻地(へきち)といわれる地方がかつて交通の要衝であったこと
年貢とは米ばかりで納められたのではないことなど、中世の持つダイナミックさにも驚きます。
こうみると、漁村・漁民も複合経営の「海村・海民」として取とらえた方が適切です。
『失敗の本質』(戸部良一ほか 中公文庫)
いまでは「文庫本」にもなり、小池東京都知事の愛読書として挙げられてからヒットしています。
事例研究なので読みやすく、旧日本軍の組織の在り方を通じて
日本の組織にある「決定的弱点」を分析しています。
システム思考の欠如、コンテインジェンシー・プラン(緊急時の対応策)のないこと
戦力の逐次投入によるマイナス効果、個々人の能力の過大評価、
結果より情とプロセスの重視といった「負けるべくして負けた原因」を明らかにしていて大いに参考になります。戦略思考重視のビジネスコ-スには、必読の書でしょう。
もう一つおすすめしたい『英語物語』(文藝春秋社)の方は、要点だけを紹介します。
英語は、情報交換の道具として国際化し、全世界で8億~10億人が英語を話すといわれています。
この英語は、決して世界一律ではありません。
必要な意思伝達の範囲内で、変更・簡略化がなされています。
Japanese English 、Chinese Englishなど独特の英語ができ、定着してきました。
そのなかで最も楽しいのが「African English」です。
例えば<good>の比較級は、<better>ではなく<good-good>、最上級は<good- good-good>と
わかりやすく変化し、過去–現在–未来も、現在形に<did>をつけて過去形、<will>をつけて未来形となります。
共通語の英語は一つだけではない、自信を持ちましょう。
.............................................................................................................................
【第40回】円筒分水ー水を運ぶ、水を分ける
「円筒分水」という言葉を知っていますか?
限られた農業用水を農地面積などに応じて公平に分配する装置のことです。
天然の河川、沼沢に頼っていたころは水が安定的に確保できるかどうかが死活問題で
しばしば命に関わる「水争い」にもなりました。
さて話は飛びますが、子どもたちにお菓子や果物を分けるときに
大きい、小さいでケンカになることがよくありますが
「バウムクーヘン」のように円形の場合には、あまりもめません。
真円(まん丸)、半円、1/4の円、1/8の円と切り分けやすく
誰にも明確で公平感があります。
円筒分水は、この理屈での「公平分配」の極みでしょう。
<サイフォンの原理>で引いてきた水を円筒の中央に噴出させる
高いところから引いた水を低いところに落とし、再び持ち上げると元のレベルまでは自然に上がります。
この原理を用いて、円筒形の枡の中央部に水を噴出させます。
導水→落下→上昇→噴出の順番です。
この水をあらかじめ合意・分割された円面積に応じ溢れさせて満たします。
枡の深さは一定ですから、受け取る水の単位当たり容量も均等分割になります。
そして、満たされた水量は、それぞれの導水路へと流れ込んでいきます。
各地の円筒分水
小さな装置だと思われがちですが岩手県奥州市・胆沢の円筒分水工は、1957年設置
直径は31.5mのコンクリ-ト製で、毎秒16トンの流量を2本の用水路へと流し
7400haの農地を潤す巨大なもので、胆沢平野土地改良区が管理しています。
観光ポスタ-で有名な熊本の通潤橋用水は、<小笹円形分水>(1956年)で分けられ
長野の塩尻には、4ケ村を潤す<四ケ堰円筒分水>(1934年)があります。
インターネットで検索すると、新潟にも①魚沼の佐梨川左岸(1959年) ②村上の神納(1974年)
③平林(1974年) ④長政乙金尾(1994年) ⑤柏崎の鍋田分水工(1972年) ⑥糸魚川の東側用水(1960年)と
多くの円筒分水があります。
NAFUでは、「新潟の地域とくらし」の講義で「新潟の水土を拓く」を学習します。
ゲスト・スピーカーの先生からは、円筒分水についてもお話があるかもしれません。
.............................................................................................................................
【第39回】中山間地域の活性化に向けて
中山間地域とは
中山間地域とは山間地域とその周辺といってもよいでしょう。
傾斜地が多く、農業生産には不利な地域で「条件不利地域」とも呼ばれます。
しかし、現実の数字面では農業生産や地域社会の発展には欠かせない大きな地位にあります。
国土面積の7割、総人口の14%
耕地面積・農家数・農業粗生産額では4割、農業集落の5割のウエイトを持つ重要地域で
「生命地域・Bio-region」とも称されます。
多面的機能の発揮への支援
これらの地域がしっかり維持されていないと、国土の保全、多様な生態系、自然環境、伝統文化 などで
支障が生じるのため「食料農業農村基本法」(35条2項)にも
「適切な農業生産活動が継続的に行われるよう農業の生産条件に関する
不利を補正するための支援を行うこと等により多面的機能の確保を特に図るための施策を講ずる」と
書かれています。
EUなどは、はるか昔から「条件不利地域対策」を重視してきました。
わが国の財政支援策としては、かなり自由な用途に使える「中山間地域等直接支払い」があり
全国で、996市町村、農地面積66万haが対象になっています。
田園回帰の傾向が出てきた内閣府が、都市住民に対し「農山漁村へ定住したいか」とアンケートしたところ
平均で3割、20歳台では4割が「希望する」との回答でした。
ヨーロッパでは、美しい村づくり=「農村計画制度」が充実しているからでしょう。
積極的に都会から田園地域に移住・定住する人が多いのです。
イギリスの南部やドイツ・バイエルン地方の農村地域は、ゆっくりと人が住むのにふさわしい美しさです。
地域おこし協力隊が活躍
日本でも、都市地域から過疎地域等へ生活の拠点を移した者を地方公共団体が隊員として委嘱し
地域協力活動を行いながら、いずれ地域への定住・定着を図るという例が増えてきました。
実際にも、20~30歳台が7割、女性も4割で、全体の6割が任期終了後も同じ地域に定住しているようです。
もともと地域社会は資源の宝庫、地元の人には見えていないことも多いのですから
その地域以外のとくに若い人の知恵や力を借りることで
地域社会の将来に向けた発展につながるのだと思います。
.............................................................................................................................

【第38回】カツオの回遊と水産物の産地市場
江戸の初ガツオ
“目に青葉 山ほととぎす 初鰹” 旧暦の4月ごろ(いまの5月ごろ)に、伊豆沖にやってきます。
獲られたカツオは小田原、鎌倉、三崎湊などに陸揚げされて馬や舟で江戸へ急送されます。
ムカデのように櫓(ろ)を出した「八丁櫓(はっちょうろ)」の快速船(8人で櫓を漕ぐ)に積んで
江戸湾を突っ切って、日本橋魚河岸に向かうのです。
コールドチェーンの整備されていなかった当時は、スピ-ドだけが頼りで
また早ければ早いだけ値も高く、最初のカツオに1尾10万円近い値段がつくこともあったそうです。
カツオの回遊路
日本沿岸のカツオにはいくつかの群があり、主な2群の回遊路は
3月の先島諸島沖(西表島、石垣島)→4月の沖縄、奄美、トカラ諸島→5月の鹿児島沖へ。
別の群は、5月の伊豆諸島沖→6月の房総沖へ、そして、7月には、宮城県の金華山沖、三陸沖
やがて9月には、北海道沖のエサが豊富で黒潮、親潮の境目に達します。
8月ごろからは、エサを十分に食べて南下する個体も多くなり、これが「下り鰹」です。
一般に、痩せたカツオは鰹節に、下り鰹は生食に向くといわれます。
漁港と水産物産地市場
『港町ブルース』(1969年)には数多くの漁港が登場しますが
統計上の水揚げの多いのは焼津、銚子、八戸、境、枕崎あたりベスト5でしょうか。
<伊豆沖と江戸>のような狭いつながりの場合は産直でも済むのですが
いまのように1年間を通じて広くカツオの漁獲を続ける漁船の場合には
魚=漁場の移動に対応しながら、漁獲の都度、最寄りの漁港=「水産物産地市場」に立ち寄って
魚の陸揚げ→販売・入金→船員給与の支払い→燃油、漁具、エサの手当てなどが不可欠になります。
そうでないとつぎの漁場への出港もできません。
この機能・役割を果たしているのが「産地市場」です。
農水産物卸売市場の役割
消費地市場も産地市場も、基本的機能は共通です。
集荷→評価・販売(価値実現)→分荷・配達などですが
加えていまでは金融(必要な費用の用立て)、情報収集・提供などの機能も求められます。
モノ、金、ヒト、情報の集積が市場の優劣を決めるのです。
物流面だけを見て「産地市場はムダ、産地―消費地の直結が望ましい」というのは現実的ではないでしょう。
時代の変化と流通、今後の行方には目が離せません。
.............................................................................................................................
【第37回】食べものは音でも味わう
人間の五感
甘味、塩味、酸味、苦味、旨味と5つの「食味」は、すでにお話ししました。
私たちは、食事を「五感」でも味わいます。
五感は、①視覚、②聴覚、③嗅覚、④味覚、⑤触覚です。
手に伝わる感触を言葉で表現すると、たとえば「寿司をつまむ」「蕎麦をたぐる」といった具合になります。
ちょっと脇道になりますが、「将棋を指す」「囲碁を打つ」と、こと・ものと感触はセットなのです。
温度で味わい、音でも味わう
和食文化に詳しい知人の話によれば、ごはんや味噌汁、牛乳の温度なども
食事を美味しくいただくポイントだといいます。
また、温度は、食材の香りを高める作用もあります。松茸の土瓶蒸しがぬるければ興覚めです。
さらに、日本人の食事が幸せなのは「音」で
「味噌汁を啜る音、漬けものを噛む音、蕎麦を啜る音
数の子を噛む音などを聞くことで食欲がそそられるのです」
とも指摘しています。
その方が格段に美味しい手段である「箸」を使うことで食べ物を啜(すす)って食べることができる、
日本人は幸せだということでしょう。
見た目も肝心
順序が逆になりましたが、視覚も大事です。
徳島の上勝町がお皿に盛られる食事の彩りとして「木の葉っぱ」つまり
青葉、若葉、紅葉を生産・販売しているのも
兵庫の御津町が梅の花のつぼみで「箸置き」を創って
売り出したことがあるのも視覚に訴えているのです。
.............................................................................................................................

【第36回】お米を研ぐ、包丁を研ぐ
お米を研ぐ
「洗う」のではなく「研ぐ」のは
「お米とお米をすりあわせて白米の表面に残っている糠(ぬか)を取るため」です。
糠には油分が含まれ酸化もしやすいので、洗うだけではきちんとは取れず
味、においに影響してごはんは美味しく炊けません。
丁寧に研ぐ=こすり合わせる、これで美味しくなるのです。
最近は、精米の工程などであらかじめ糠を取り除いてある「無洗米」が多くなりました。
その製法は企業秘密のようですが
糠で糠を取る、水洗いする、ブラシでこするなどともいわれます。
家庭では研ぐ手間が省ける、節水になる、とぎ汁による水質汚濁が防げるといった利点もあります。
炊飯器にお米を入れて水を加えスイッチを押すだけですから
これなら、タイマーで炊きあがり時間を決めておけば、学校給食でも自分たちで簡単にごはんが炊けますね。
包丁を研ぐ
刃物も砥石にこすって金属部分を薄くし、切れやすくしますから
こちらも「研ぐ」といいます。
研いで切れ味が鋭くなった包丁ならば、野菜や魚など料理の素材の細胞をできるだけ崩さずに調理できて
本来の味を引き出すことができます。
タマネギもよく切れる包丁であれば細胞を崩さないので涙が出ません。
ちょっと実験してみてください。切れる、切れないなど、両方を比較しましょう。
燕の「洋食器」
さて、刃物のついでに、ナイフ、フォーク、スプーンの話をします。
新潟・燕の「洋食器」は、世界一といってよいでしょう。
もともとは、刃物や「和釘」、唐招提寺や薬師寺の木造建築に用いられる<腐食しにくい釘>の技術が
始まりです。
NAFUの学生食堂ではこれを使うことにしました。きっと快適ですよ。
わが国伝統の刃物、日本刀に由来する安来や三木の刃物は
無類の切れ心地で、食品素材の持ち味をしっかり料理に伝えます。
私が持っている三木の包丁セットでも、出刃包丁で氷見ブリをさばいた時の切れ味が忘れられません。
.............................................................................................................................
【第35回】消費者の4つの権利
ケネデイ大統領の特別教書
1962年3月にアメリカ合衆国のケネデイ大統領は、議会へ「消費者の利益保護に関する特別教書」を送りました。
その中で、大統領は「経済機構の中で最も大きな一群をなすものが消費者であり、(中略)
(政府は)その要望に耳を貸し、その利益を増進させる義務を負う」と述べています。
具体的な権利として掲げたのは、
①安全を求める権利、②知らされる権利、③選ぶ権利、そして、
④意見が反映される権利 (the right to be heard)です。
その後フォ-ド大統領が「消費者教育を受ける権利」を加え
世界消費者機構(Consumers International)も3つの権利(需要への対応、環境の保全、被害の救済)を加えて
いまでは「消費者の8つの権利」ともいわれるようになりました。
消費者の関心の変化
時代の変化とともに、消費者の関心領域は
量から質、価格、安全・安心、健康・美容、機能へと移りつつあるように見えますが
もともとの「4つの権利」を貫いている底流、基盤の考え方には、いささかの揺るぎもありません。
循環の輪(和)の再構築
これまでとかく分断しがちであった「食と農」、「消費者と生産者」、「都市と農村」の関係を修復して
循環の輪(和)を再構築することが求められますし
また生産者にも、消費サイドを強く意識することが、遠回りのようでも
結局自らの利益につながることを確認したいと思います。
NAFUが基軸に据えている<マーケット・イン>は、
<コンシューマー・ファースト>(消費者優先)にもつながるのです。
.............................................................................................................................
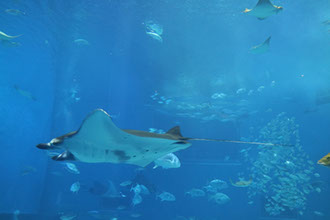
【第34回】出世魚 おコメも魚も呼び名が変わる
呼び名が変わると調理法も変わり、場合によるとまったく異なる食品としての
新たな商品価値が与えられることもあります。
コメ
稲→モミ米→玄米(モミ米x0.8)→精米(玄米x0.9)→ごはんと変わり、その途中
①稲からは「稲わら」が採れ、かつては、縄、ワラジ、蓑(みの)などが作られ
いまでも飼料、敷料に用いられます。
「母さんの歌」に出てくる「お父は土間でワラ打ーち仕事、お前ーもがんばれよ-」というのは
ワラを木槌でたたいて繊維を柔らかくし細工しやすいようにする作業です。
②のモミ米から約2割分離する「モミ殻」は、田畑にすき込んだりして、肥料にする、家畜の敷料にもなります。
③玄米を精米するときに約1割出る「米ぬか」はビタミン、ミネラルが豊富なほか、
脂肪分が高いので「米ぬか油」が製造されます。
玄米自体も最近は優れた健康食として人気がありますし、
米ぬかも、ビタミン、ミネラル、繊維が多いので、これを活用し、ブラン・ケーキなどのスイ-ツが人気です。
なお、国際市場は、玄米ではなく精米取引が一般的です。「麦のヌカ」は<ふすま>です。
ブリ
ワカシ→イナダ(30cm)→ワラサ(60cm)→ハマチ→ブリ(90cm)と
大きく成長するにつれて呼び名が変わります。
なおハマチの名称ですが、関西ではハマチは養殖もの、関東では、ブリとのサイズの違いとされています。
これは、ブリ養殖が関西で始まったからでしょう。
ボラ
オボコ→イナ(30cmまで)→ボラ(30cm以上)→トド(最大級)の順番です。
なお、ボラのタマゴの加工品を「からすみ」といって、酒のつまみなどに珍重されます。
ときに「トドのつまり」という言葉が使われますが
これは、海棲哺乳類の「トド」ではなくて、<ボラの成魚=これより上はなしの最大級>で
「トドの詰まり」なのです。
青森・五戸の女性
古い話になるのですが、民俗学者の宮本 常一さん、能田 多代子さんが
青森・五戸での女性の呼び名の変化を取り上げたことがあります。
ワラシ→メラシ→アネコ→アッパ→オンバ→エヌシ→ババという変化ですが
ここには、「出世」という感覚はありません。
それぞれの年齢、一家の内外での立場で名が変わるというものですから
日本の古いしきたりと女性の関係なのです。調べてみましょう。
.............................................................................................................................
【第33回】上中下、前後、上る・下る
上中下
「上越」という言葉で何を想像しますか。
群馬県と新潟県を結ぶJR「上越線」、
こちらは、旧国の上州の<上>(上野=上毛の国)と越後の<越>を取っています。
また、新潟県の直江津と高田が合併した新地名の「上越」市の場合には
国の「中心」である「京都」から見た方向感覚です。
つまり、京都に近い方が「上」で、離れるに従って、「中」、「下」となっていきます。
新潟県の地理区分でも、上越市のある辺りを上越地区と、長岡市がある辺りは中越地区、
新潟市がある辺りは下越地区と呼んでいます。
そして、佐渡を入れて、新潟は、4地区に区分されています。天気予報もそうなっていますね。
前(中)後
これも京都に近い方が「前」、離れるに従って、「中」、「下」となります。
北陸地方は、京都に近い順に<越前>(福井)、<越中>(富山)、<越後>(新潟)となりますが
最初は、「越(高志)の国」一国でした。
7世紀末に3国に分かれその「越前」から、能登(718年)、加賀(823年)が分離されたのです。
東北地方では、羽前(山形)、羽後(秋田)、陸前(宮城)、陸中(岩手)、陸奥(青森)という順番で
関東地方では、千葉が、上総、下総、安房と分かれます。
陸路からいえば下総の方が京都に近そうにも思えますが
かつては相模(神奈川)からの海路が主で、こうなったのでしょう。
平氏に追われた源頼朝も海を渡って房総半島に逃げ込みました。
隅田川にかかる「両国橋」は、武蔵、下総の2国の国境が名前の由来です。
上る・下る・下(くだ)らない
京都から江戸へ行くのが「下り」、江戸から京都は「上り」です。
いまは東京へ出てくることを「上京」といいますが
天皇陛下のおられる「東の京」が東京ですから、「上る」となるのです。
その一方で、京都を漢、隋、唐時代の都「洛陽(らくよう)」に見立てて
京都に向かうことを「上洛(じょうらく)」ということもあります。
つぎに、「下らない」の語源です。
かつて、日本酒の名産地は、上方の伊丹、池田、灘で
そこから、大消費地の江戸へと「樽廻船」などで運びましたので
美味しい酒を「下り酒」、美味しくないのは「下らない」と称しました。
上方の新酒を競争で早く運ぶ「新酒番船」これが大人気だったと
平岩弓枝さんの『御宿かわせみ』(初春弁才船)にも登場します。
関東の酒は「地回り悪酒」などといわれ評価が低く
幕府も米を与えるなどして品質向上に努めましたが、結果はさんざんだったようです。
.............................................................................................................................

【第32回】北前船と高田屋嘉平衛たち
ここでは、江戸時代の末期、日本近海の海運に大活躍をした3人のお話をします。
北前船の航路
造船技術、操船技術の発達に従って、かつてのような「地乗り」(沿岸航行)から
はるか沖合、場合によると佐渡の西側を追い風で速度を上げつつ走るルートも利用されるようになります。
北陸の<福浦・輪島→伏木・小木→今町→新潟→酒田>の路線に対して
<福浦(→ 小木) →酒田>の超スキップ・ルートの千石船が登場します。
「千石」とは、重量でなく容量(カサ)で、コメで換算すると
1石=150kg=0.15t1000石船は100~150t積みですが
幕末には、2000石を超える大型船も出てきました。
高田屋嘉平衛(1769~1827年)
淡路島の出身、兵庫湊を拠点としました。
大坂~江戸の樽廻船(日本酒)の水主(かこ)で財をなして、その後「北前船」を経営します。
輸送の請負で運賃を取る回船業の手法を改め、自らリスクとリターンを引き受ける「買取制」に転じて
さらに、函館(箱館)から国後・択捉の航路を拓き、漁場経営でも成功しました。
根拠地とした函館市宝来町(函館山の麓)には、いまも大きな像が建っています。
大黒屋光太夫(1758~1821)
伊勢国白子(三重県鈴鹿市)を拠点とした回船の船頭で、江戸回り航路で漂流し
アリューシャンのカムチトカ島に漂着しました。
「ロシア帝国」の「サンクトペテルブルグ」に連行されて皇帝にも拝謁、9年半後に帰国を果たしました。
鎖国時代でも、日本人の足跡は、世界各地に広がっていたのです。
銭屋五兵衛(1774~1852)
北前船を駆使した加賀藩の御用商人・海運業者です。
「海の百万石」といわれ全所有船数は200艘以上のうち、千石船=20艘以上、
大陸との密貿易の疑いをかけられて80歳にして刑死しました。
五兵衛は、その財力で河北潟の干拓(稲作経営)も手がけましたが
完成を見ることはありませんでした。
江戸時代の新田開発、干拓、水路建設は、開発者に莫大な利益をもたらすので
豪商が乗り出すことも多かったのです。
越後平野を豊穣の地に変えた「信濃川の大河津分水」(日本海への水路誘導)も江戸時代に着手されました。
新潟の各地には、水土を拓く土地改良事業の遺産があります。
.............................................................................................................................

【第31回】ヒトは陸(おか)の道、モノは水の道
日本海の海上交通
鉄道網が整備されるまでとくに大量貨物の輸送は、川や海を経由するのが主流でした。
11~12世紀には、日本海に海上交通の大動脈が形成され始め、十三湊、敦賀、若狭、小浜などには
大陸からの入津も盛んでした。
琵琶湖経由や瀬戸内海経由の航路で、京都、大坂には大量の物資が円滑に搬入されて
瀬戸内海の「兵庫湊」(神戸)に出入りする船数は、バルト海
北海に栄えたヨーロッパ・ハンザ海運同盟のどの湊よりも多かったといわれています。
日本海+瀬戸内海の北前船航路は、河村瑞賢によって17世紀に完成しました。
「下り荷」(北国方面)は、米、酒、綿、煙草、塩、紙、砂糖、蝋燭、鉄、
「上り荷」(畿内方面)は、ニシン粕(棉作の肥料)、数の子、身欠きニシン、
干ナマコ、昆布、干ダラなどでした。
太平洋岸航路の出遅れ
操船・航行の方法には、沿岸の陸と山を見ながら走る「地乗り」と
離れて走る「沖乗り」の2つがありますが
わが国では、江戸時代における船の大きさ制限、性能の限界などから、「地乗り」を主としてきました。
太平洋沿岸ではこの航行法だと、海路の途中にいくつかの決定的難所(灘)があり
さらに、荒天時に停泊する「避難港」が少ないという弱点がありました。
日本海と太平洋ではその危険度から、幕末に至っても運賃格差(リスク・プレミアム)があり
江戸への輸送では、太平洋航路は距離が短いにもかかわわらず、運賃は高かったようで
高リスクでは、運送業者が貨物を買い取って運び、販売する方式も採り難いのです。
平岩 弓枝さんの『御宿かわせみ』(初春弁才船)には航路中、遠州灘、熊野灘が難所で
東北から江戸への運賃は、西回り(713里)で1石21両、東回り(417里)で22両2分とも紹介されています。
日本海の海運が本流であり、「<裏>日本」などと呼んではいけません。
北前船の買取い制・運送
日本海を往復する北前船の場合には、各地域、湊で
特産物の買取り、販売を繰り返して利益を生み出すチャンスも多いのです。
このように、北前船での特徴は「輸送+買取+販売制」
貨物の運送賃だけを受け取る「請負制」と違いがありました。
リスクとリターン、どう判断して経営するのか、現代のビジネスにも共通します。
.............................................................................................................................

【第30回】日本の棚田 新潟の棚田
棚田百選
「棚田は日本のピラミッド」といわれることがあります。
先人たちが山を拓き、石垣を築き、水を引き、畔を盛り
気の遠くなるような年月を重ね、棚田が作られました。
いまから約20年前の平成11年(1999年)5月、全国から応募のあった36府県117市町村(当時)にある
134カ所の棚田が「棚田百選」として認定されました。選考の基準は国土保全、環境保全でした。
継続して生産活動を行うことを通じて棚田が維持され、国土、環境保全が実現すると考えたのです。
同時にそのための費用として、地域のいろいろな活動に自由に使える
「中山間地域等直接支払い交付金」も準備されました。
新潟の棚田、隣県の棚田
この地域で認定されているのは新潟が7か所で、隣県では山形が3、富山2、長野16です。
なお、群馬、福島では認定がありません。
新潟の内訳は旧市町村で
①松之山町・狐塚、②高柳町・梨ノ木田、③大島村・蓮野、④高柳町・大開、
⑤下田村・北五百川、⑥安塚町・上船倉、⑦高柳町・花坂です。
とりわけ松之山は有名で、英国人写真家のジョニー・ハイマスさんの作品「たんぼ」(1994年)にも登場し
息をのみ、心を打つ美しい風景が多く取り上げられています。
棚田の保全活動
立地する地域の多くは高齢化、過疎化が進み、維持が困難という状況も出てきました。
百選に認定されてから、例えば、姨捨、輪島、千葉大山のように、
棚田のトラストやオーナー制が実り交流が盛んになり
資金的、人的な応援もあってよい方向の棚田もあるのですが
一方では、撮影の人々が水田に勝手に入り込み畔を荒らすなどで、
「来てほしくない」という声も聞きます。貴重な財産の維持・承継をよく考えましょう。
NAFUの授業で棚田を紹介
新潟には、佐渡などに、百選に認定されたもの以外の棚田が数多くあり
地域の人々や都会からの応援団に支えられながら維持・承継されています。
NAFUでは、棚田について、歴史、特徴、活動などを、1年次の授業で学習します。
.............................................................................................................................

【第29回】「虫送り」と日本人の自然観
農業と病虫害は敵対関係であるように見えます。
そのため、「退治」とか「駆除」という言葉が使われます。
江戸中期の稲作害虫「ウンカ大発生」(1732年)は、大凶作をもたらしました。
さしたる農薬もなかった当時としては神頼みもやむを得なかったのかも知れず
そのころに始まってその後に広く定着したのが「虫送り」行事です。
「虫送り」行事
「虫送り」「イナムシ(蝗=イナゴ)送り」「さねもりさま」と称される農村行事は、全国各地に残っています。新潟でも、柏崎市の高柳町などでは、ずっと続けられているようです。
6月の終わりから7月半ばまで田植え後の農閑(田休み)の時期に子供たちも参加します。
松明をかざし、鉦(かね)、太鼓ではやしながら、畔道を辿って集落(むら)の境まで練り歩き
「疫病神を形どったワラ人形」を集落の外へ放り出して追い払うのです。
そのときの掛け声は、たとえば
<ネ-ムシ(根虫)、ハ-ムシ(葉虫)、飛んでいけ、サネモリどんのお通りよ>とか、
<イナムシ送りや、おくりや、おくりや>、
<ドロムシ(泥虫)、出てけ、サシムシ(刺し虫)、出てけ>などで
行事の最後にはご馳走も待っています。それでは、なぜ「さねもりさま」というのでしょうか?
サネモリさま
虫送り行事は、木曽義仲軍と戦って、無念の最後を遂げた平家方の武将「斉藤別当実盛」に由来しています。
1183年篠原の合戦で、実盛は稲につまづいて倒れ、打ち取られたとの伝承があり
その遺恨から死後は稲を食う害虫になったといわれます。
それを供養することで虫害を避けようとする「怨霊鎮魂」の行事が生まれたのでしょう。
日本人の自然観
退治、駆除するのではない、むやみに生き物を殺さないで、「避ける」、「逃がす」、
「追い払う」のが、どうやら日本人の本来の自然観のようです。「蚊遣り」も「鳥追い」も同じで
柏崎市高柳(門出・田代)の若者たちからの便りには
「稲の害虫を追い払うこの冬の恒例行事<鳥追い>を1月14日に」とありました。
「山椒大夫」では、佐渡の地で、盲目の母親が、「疾うとう逃げよ、追わずとも」と鳥を追っています。
.............................................................................................................................

【第28回】疏水百選と新潟の疏水
地球10周分の用排水路
農業・農村は、長らく、「水」には苦労してきました。
越後平野が豊饒(豊穣)の地なのも信濃川の管理(大河津分水)
用排水路網の建設・運営の歴史があったからなのです。
新潟は「ガタ(潟)」、川より低く排水の悪い土地です。
周囲を土手で囲む「輪中」、水車での排水、胸まで泥に浸かる田植え、舟上からの稲刈りは当たり前でした。
日本には40万km(地球10周分)がありますが、この人工水路は、2000年に亘って
水土を拓いてきた「水のネットワ-ク」です。
「疏水(そすい)」とも「堰(せき)」ともいわれています。
三大疏水
明治に入って人口が増加し、農業、工業の発展には水の確保が必須になってきました。
多目的の「ダム、水路、発電所」が必要になったのです。
1880年代になると、三大疏水の①安積疏水(1884年)、②那須疏水(1885年)
③琵琶湖疏水(1890年)があい次いで完成し、農業用、工業用、飲料用に寄与します。
水の歴史は、何10kmも離れた河川から水を引き豊穣(ほうじょう)の地に変える難工事の連続でした。
疏水百選
農村地域の高齢化が進むと「疏水(そすい)」「堰(せき)」の維持・管理が難しくなり、
地域での非農業者や都市の住民の応援も必要になりました。
疏水は、農業の用排水だけではなく、保健休養、美しい景観など多様な役割を果たしてきていますから、
日本百名山、名水百選、棚田百選にならって、
平成17年(2005年)には「疏水百選」が110ヶ所指定されました。
選定基準は、①農業・地域振興、②歴史・伝統・文化、③環境・景観、④コミュニテイで、
新潟では「亀田郷」と「加治川用水」が指定されています。
亀田郷は、かつて「芦沼」ともいわれましたが
昭和34年(1959年)までの土地改良事業で見違えるようなコメの生産地になりました。
いま「丸潟新田ビオト-プ」として、環境保全にも貢献しています。
「潟のデジタル博物館」にアクセスしてみましょう。
加治川用水は、干拓によって生み出された1700haの新田です。
洪水と渇水に悩まされましたが、昭和49年(1974年)に完成した土地改良事業で豊かな土地に変わりました。
加治川用水はNAFUにも近い新発田、聖籠にありますから、訪れてみてはどうでしょうか。
.............................................................................................................................

【第27回】モンキードッグと鳥獣被害
鳥獣被害
シカ、イノシシ、サルなど野生鳥獣による農林業被害は、毎年約200億円もの高額になっています。
防御、管理、処理のための予算も、100億円を超えます。
狩猟免許の所有者が高齢化・減少して駆除ができない、森林の手入れが足らず木の実が乏しくなった
観光客などが餌付けをし鳥獣が人間を恐れなくなったことなどが背景にあります。
モンキードッグ
普通の犬を数ケ月間程度訓練し、サルが里に現れると吠えて山に追い返す役割を果たす
「モンキ-ドッグ」が増えてきました。
始まりは2005年に長野県大町市で導入され、現在では、50匹程度になっているようです。
導入地では、サルが群れで田畑に現れることがなくなったと聞きます。
田畑や集落を柵で囲むより犬がサルを追い払う方が自然だとの考え方です。
私もドライブ中に子ザルの飛出しが見られる山道で「モンキ-ドッグ訓練中」の看板を見かけたことがあります。
一方、近隣ホテルのレストラン前庭で30匹ものサルの群れが人を恐れることなく、被害を加えることなく
木の実を啄ばんでいる光景もありました。
大ザルが、クリやドングリの木によじ登って揺さぶり、木の実を子ザルやメスザルに落とす。
食べ終わるとひとしきり遊んでは次のエサ場に向かいます。
ホテル側の説明では、「ここは餌付けをしていませんので大丈夫」とのことでした。
人間と動物の共棲
山に実のなる広葉樹を確保する、そのための手入れをする、
群れの数が増えないよう気をつけ管理(間引き)する、里では「人間は怖い」と感じさせ、餌付けはしない、
こうして、人と動物は共生ができます。
今西 錦司さんは、『生物の世界』で人と動物の「棲み分け」を説明します。
エサが入手できて、生活もできる森林管理のあり方が問われているのです。
米国の「ヨセミテ国立公園」では、餌付けは厳禁、キャンプ地でも食品の残りは持ち帰る、
人が来るところではエサになるものを一掃すると徹底しています。
捕獲目標の設定、ジビエ食肉利用率の向上、狩猟・管理できる人材の養成も必要です。
.............................................................................................................................

【第26回】ワサビの正しい食べ方
ワサビの種類
ワサビは田や畑、林間で栽培しますが、観光ポスタ-に見られる美しい光景は、
信州・安曇野や静岡・伊豆の「わさび田」です。強い日差しを嫌うようで
日よけ「寒冷紗」がかけられています。
2017年には、静岡わさびの伝統栽培などの8地域が
日本農業遺産に認定され、FAOの世界農業遺産も狙っています。
最近は和食文化の普及に伴い、海外でも大人気です。
生産量は長野県が856t(38%)第1位で、ついで岩手518t、静岡505tがベスト3です。
意外なことに東京が33t、北海道も32tと善戦です。
3月中旬の安曇野、白い花が咲き「春告げ花」といわれます。
ホースラデイッシュ
ロ-ストビ‐フの薬味になる「ホ-スラデイッシュ」は西洋ワサビといわれ
アブラナ科「わさび大根」ですが、洗練された味の点では日本の田ワサビには及びません。
チュ-ブ・ワサビなどの増量材に使われ、和種は「本ワサビ」とも称します。
ワサビの辛味成分
唐辛子の辛味成分である「カプサイシン」とは異なるようで、わさびの中の「シュグリン」が
すり下ろすときに酸素に触れて生じる辛味だといわれています。
殺菌機能などもあって、古代から使われていたとの記録もあります。
ワサビの正しい食べ方
老舗のそば屋でもりそばを注文したときに、店員にワサビの正しい使い方を説明されることがあります。
おろし金、<ワサビ芋>、砂糖のセットが出てきて「砂糖を少々混ぜながらおろしてください」
「おろしたワサビは、タレつゆに入れてかき混ぜずに、箸先につけるか、そばにまぶしてお食べください」
といわれるのです。
<なんだか面倒くさい>が、確かにおいしくなる。
空気に触れてより辛味が出る、お汁粉に少量の塩を入れて砂糖の甘味を引き立たせるのと同じで
調理の妙なのでしょう。
.............................................................................................................................

【第25回】英語こぼれ話 その2
その2では、英語の歌や映画や音楽の話をしましょう。
ここに出てくるようなシャレた文句を覚えて使うことで、英語に強くなれ、ちょっとした優越感に浸れます。
ただし、記憶だけが頼りですから、正確さのほどはご容赦ください。
金髪のジニー
ご存知フォスタ-の名曲の一つですが、「金髪」って英語で何というのでしょうか。
ふつうは「ブロンド」(Blond)と思いますよね。
しかし原曲では違っていて、正解は「薄茶色(栗色)の髪」で
たぶん日本人の金髪好きに合わせて意訳(異訳?)をしていたのでしょう。
原曲の実際の歌詩は、つぎのとおりです。
“I dream of Jeanie with the light brown hair” でした。
ちなみに、複数形 hairSではありません。
つぎはスミレですが、宝塚歌劇で有名な「すみれの花咲くころ」は
オ-ストリア→フランス→日本と渡ってきて、花もニワトコ→リラ→スミレと変わりました。
1929年のフランス語の歌詞は、“Quand refleuriront les lilas blancs”(白いライラック)です。
愛しのクレメンタイン
この歌は「荒野の決闘」の主題歌なのですが、日本では曲だけを拝借し
「雪山讃歌」としてポピュラ-になりました。
さて、気に入ったセリフですが
主人公がクレメンタインのことを「愛している」といえず遠回しに
“I sure like your name , Clementine”(クレメンタイン、いい名前だ)と控えめにいう場面が印象的でした。
ここで、歌の内容ですが、こちらも勉強(知識)になります。
クレメンタインは、“49ers”“miner’s daughter”1849年の
カリフォルニア・ゴ-ルド・ラッシュ時代の金鉱夫の娘という設定です。
49ers(fourty-niners)は、シアトルのフット・ボ-ル・チ-ム名に残ります。
結局、娘は溺れて亡くなってしまいますが、歌詞には“Her shoes were number 9”と出てきますから
靴の大きさは26~27cmのビッグサイズ、なんとも不思議な歌ですね。
気になることをもう一つ、亡くなってから丘の中腹に葬られた娘の遺体は
肥料になって花を咲かせる、Fertilizedという農業用語が出てくることです。
(閑話休題) 「お墓関連」の英語表現とそのニュアンスの違いを調べてみましょう。
(1)Cemetery(ア‐リントン墓地)(2)grave yard(フォ-ク「花はどこへ行った」)
(3)tombstone(西部劇・仮の地名)(4)boot-hill(bootは単数、片足が墓標代わり)
(5)pushing-up-daisies(ヒントは、fertilizedにあります)
※(1)(2)(3)は分かるとして、(4)(5)は俗語に近く難しい、さあ、どうでしょうか
.............................................................................................................................

【第24回】鋤・犂(すき)と鍬(くわ)、そして<トラクター>
連載11回目の「学長コラム」(アメリカ映画に見る食料・農業)において
それまでの<馬と犂(すき)>に代わって登場したトラクタ-が農地を深く耕し過ぎたために
土壌が流出(エロ-ジョン)、ダストボ-ルの原因にもなり農業不況をもたらしたと述べました。
そこで今回は、日本における農具としての鋤(犂)、鍬、鎌と農地・農業生産力の関係をお話ししましょう。
注)大雑把には、<手鋤き>と<牛・馬犂き>と分けて説明されています。
中世までの農業は「鋤」(すき)が主流
日本は、なにかと中国の影響を大きく受けています。
農業も同様で中国・華北の「乾燥地域」での農法がそのまま取り入れてきました。
つまり、土中の水分(湿度)を保つには浅く耕す必要があり、それには鋤が適していたのでしょうが
国土の狭い日本では「広く浅く」のやり方では単収の増加に限界がありました。
深く耕す→根が深くまで伸びる→土壌の養分が広く吸収できる→肥料を多く与えても効果が上がる
→やはり深く耕す農具を作って使おうという流れで生まれて
改良・工夫を重ねてきたのが各種の「鍬」だったのです。
近世は「鍬」(くわ)の時代
もちろん、中世にも鍬のようなものはありましたが、近世の江戸時代になると農作業ごとの鍬が出現しました。
耕起用、土さらえ用、中間の作業用などといった具合で、刃と柄の角度、柄の長さも多種・多様です。
これにより、日本では、棉作用の金肥、例えば、イワシやニシン粕の多投が可能になり
商品作物としての農業生産、加工、流通が活発になって、経済が大きく拡大したのでした。
現代の農業機械
アメリカでのトラクタ-の発明・普及は大戦での戦車の生産・改良を通じて
世界中に機械耕作化へのきっかけと発展につながり、日本でも経済の高度成長以来ごく一般化して現在に至ります。
また、いまでは「多目的」機械になりましたから、農地・土壌の実情に応じ
作業の目的にも合わせてアタッチメントを交換するだけで、いかなることも可能な「汎用機械」に進化しています。
さて、余談になりますが、4月のある日にNHKテレビを見ていましたら、南北朝鮮の境界線からの望遠レンズに
北朝鮮側の農業の姿、牛にひかせた犂(すき)での耕起作業が映し出されていました。
乾燥農業なのか機械化の遅れか、とても興味深い場面でした。
なお、「鎌」にも用途に応じた種類があるのですが、その話はつぎの機会にしましょう。
.............................................................................................................................

【第23回】イザベラ・バードが見た140年前の胎内地方
第1回「基礎ゼミ」の学長講話で
「胎内の歴史は古い、平安時代には、
すでにいまの中条を中心とする摂関家の荘園が形成されており
また、鎌倉時代には武士活躍の一環として『胎内・鳥坂城(とっさかじょう)』の戦いで
鎌倉幕府方を迎え撃った弓の名手・『板額御前』の奮闘ぶりを述べて
<地域の地理・歴史を知ろう>」と伝えました。
今回は、いまから140年前、明治の初期に日本の奥地を旅した英国人女性「イザベラ・バード」の旅行記から
日本と胎内地方のスケッチ・印象記を紹介することにします。
地域社会のよさは気づきにくいもの
イザベラ・バ-ドが日本へ来たのは、1878年の5月、彼女が47歳のときのこと。
その後、3ヶ月ほどをかけて、日光、会津、新潟、東北の西、北海道の南を旅しています。
そして、その日本に対する印象は、日ごろ私たちが気づかないようなことばかりでした。
美しく、清潔で誇り高い日本
・・・浮浪者はいない、みんな仕事を持っている、貧相だが優しそうな顔つきをしている、
着ているものは上等ではないが、みな礼儀正しく、勤勉である、
どこも安全で婦人がなんの危険もなく旅行できる、
女は技術や教養を身につけている、これほど自分の子どもを可愛がる人々はいない・・・といった具合です。
新潟から山形・米沢への旅
会津(福島県)から山を越え新潟に入ったバ-ドは、阿賀野川・中流の川湊から船に乗って新潟へと向かいます。(新潟の観察では)信濃川とその支流が莫大な水量と砂や岩くずをも運び、
河口は砂州でふさがれ、細い水路も絶えず浅くなって、手に負えない、と記しています。
その後、新発田、加地川(聖籠)~中条~黒川を経て、
米沢へと旅を続けるのですが、このあたりの風景の描写は、つぎのようになっています。
胎内地方は<全体として楽しげな地>
・・・貧乏そうにも見えなかったし、非常に不潔な感じもしなかった。
土はとても軽くて、砂地であった。
丘陵と丘陵との間の低地は菜園のように肥料を充分に施して耕作してあって、
えんどうのように這わせたきゅうり、水瓜、南瓜、里芋、甘藷、とうもろこし、茶、玉葱など
すばらしい作物をつくっていた。
りんごや梨の広々とした果樹園は、8フィ-トの高さの棚に横に這わせてあり
珍しい風景となっていた。東方には山頂まで森林におおわれた山脈(飯豊山脈と思われる)が走っており・・・
どうでしょうか、新潟平野も胎内も、いまの景色とほとんど変わらず、胎内地域の豊かさがよくわかります。
なお、ベタ褒めなのは、「置賜県・米沢地方」で、バ-ドは、この地方を
<穀物や果物が豊富で、地上の楽園のごとく、人々は自由な生活を楽しみ、東洋の平和郷というべきだ>
とまでいいます。
私たちは、外国人がこれ程日本のすばらしさに気付いているのですから、
もう一度、故郷を見直すべきかもしれません。
.............................................................................................................................

【第22回】マーケット・ブランドの実力
前号で、産地と生産物を組み合わせた、いわば「産地ブランド」のお話をしました。
ブランドには、生産地ばかりでなく、集散拠点=マ-ケットのブランドもあります。
流通の拠点である市場の名前で全国流通し品質にも高い、ある一定の評価が与えられているものです。
例示すれば、「下仁田のこんにゃく」、「氷見のブリ」、「下関のフグ」という具合でしょうか。
ブリでいえば、富山湾のものだけではなく佐渡ブリも、
こんにゃくでいえば、群馬だけではなく茨木も福島も、
フグに至っては、静岡・駿河湾のフグも下関に搬入されセリにかけられます。
物流面からいえば、まことに不経済、不合理に見えますが、
市場で目利きが評価して自信を持ってお勧めできる、高い価格もつけられて
消費者サイドでもガッカリすることがない産物なのです。
かつての経験ですが、千葉県産の野菜が東京の神田や太田の市場に搬入されて
そこでセリ落とされた後にふたたび千葉(大都市である千葉市)に戻って小売されるのを聞いた方から、
「なぜ地産―地消にならないのだろう?」と尋ねられたことがあります。
もちろん、千葉にも大きな市場はあるのですが、「値付け」の力が弱く、いい値段になりません。
結局出荷者・団体は東京を選ぶのです。
原則論、基本論に戻りましょう。近年の流通業界では「流通革命」とか、「ネット取引万能論」も出ています。
また、「多段階を経取引は無駄でショ-ト・カットをすれば収入も増える」という考え方も多い状況です。
でも、短い流通にしても、収入の多少は力関係での取り合いですから、
<必ず生産者の収入が増える>ということにはなりません。
もちろん、ときは移り、時代は変わりますので、産地、消費地双方の大型化や規格化や情報化の進展が
適正・公正な価格形成にどの程度の影響を与えるかで市場のあり方、存在価値も変わります。
しかし現段階では、まだまだ多数の生産者と多数の小売業者とを一つの場で結びつけ
集荷、分荷、評価、価格決定、代金決済・金融、情報提供、加工、配送などを最も効率的に行えるのは
公的な団体・機関が運営するオ-プンな市場なのではないでしょうか。
「存在しているものには意味がある」ともいいます。まず現状を検証して
それからつぎのステップに行くことを考えても遅くはないと思います。
.............................................................................................................................

【第21回】農水産物の地域表示
最近、「地理的表示」とか「GI」という言葉を耳にしませんか。
生産地の地名と農水産物・食品の名前とがセットになった商品で
その名前を聞けば必ず「それ」とわかるものです。(例:米沢牛、夕張メロンなど)
流通上も高く定まった評価が与えられ、他の生産者が紛らわしい名称を使用するのを制限したり
排除しようとするものです。
国際的貿易協定でも参加国が合意してこれを守らせる仕組みを採用しています。
日本国内でも、名称の使用制限をする農水産物が、「地理的表示」(GI)として
58の品目が指定されていますが、残念ながら、新潟県産のものは「くろさき茶豆」ひとつしかありません。
おコメが中心で、しかも長らく日本で最もおいしいという位置にあった「新潟県産コシヒカリ」が
関係しているのかもしれません。
それから、おコメは国内生産→国内消費が大半でしたから、
国際競争は念頭になく、食管法・食糧法に関わる国内表示だけで間に合っていたともいえます。
おコメの場合、「産地」「産年」「銘柄」がセットで流通します。
<新潟県・平成29年産・コシヒカリ>と表示し、<魚沼><岩船><佐渡>などは、副次的表示になります。
グロ-バル化は避けられない方向ですから、国内だけではなく、海外でも通じる表示と
それを守らせる方策が求められる時代になりました。
.............................................................................................................................

【第20回】ストレスの予防法、解消法
今回も、<閑話休題>で、いろいろな「ストレス予防法、解消法」を紹介しましょう。
新入生の皆さん、それぞれにキャンパス・ライフを楽しんでいらっしゃることと思いますが、
学習のこと、生活のことなどで、いままでとは違ったストレスも多いことでしょう。
そんなとき、どうすればよいのか、先人たちの実例に触れていきます。
ストレスを楽しむ
これは別格で、天才でなければできない技です。
読売ジャイアンツの名誉監督「長嶋茂雄」さんなどは、ストレスがかかると実にうれしそうな顔をしました。
彼の名言が残っています。「ストレスを楽しまなくちゃあ」
闘将といわれた「星野仙一」さんも同じタイプで、「プレッシャ-来い、来い」だそうです。
ストレスを有効利用する
こちらは、理知的な考え方・行動です。悪いストレスをよい行動のきっかけに転換・利用する。
ストレスが来ることは当然の前提として、どんなストレスかを冷静に分析し、
体や心の反応を整理、理解した上で、有効利用する。
女性ゴルファ-の名手「ベッツイ・キング」は、<making stress work for you >といっています。
これもなかなか難しい対処法だと思います。
次のストレスに目を向けて前のストレスを忘れる
小泉純一郎元総理の対処法です。
かつて、率直に「山のようなストレスの多さにどう対処していらっしゃいますか?」とお尋ねしたところ
「新しいストレスがやって来て、前のストレスを他の人にバトンタッチすればいい、貯めこむから悩むので、次々に来るということは、前のものはやがて忘れるということだ」
とお答えがありました。まあ、これも、大人物でないとなかなか難しそうですね。
タメ息は最良のストレス回避策
さて、もっとも身近な方法は、心療内科のお医者さんの解説によるものですが
これは、妙に納得してしまった「呼吸」による対処方法です。
<息を一つ深く吸って、大きくゆっくり二つ吐き出す>その繰り返しで気持ちが落ち着く、
これなら、誰にでもできそうですね。
体と心のシグナルを見逃すな
体を使う、ウオ-キングなども解消策としてよさそうですが
<ゆっくり歩き>では、あらぬことを考えてしまいますから、やるなら「速歩」に限ります。
そして、ストレスの限界が近づきつつあるという心と体のシグナルは必ずあります。
そのときは、直ちに専門家に相談しましょう。
私事になりますが、猛烈ないストレスを抱えた生活の中、速歩の途中で、
完全に足が止まった経験があります。ふと左隣を見ると、そこは「病院」でした。
ウソのような本当の話で、すぐにそこへ飛び込んだことはいうまでもありません。
.............................................................................................................................

【第19回】英語こぼれ話 その1
今回は、ちょっと<閑話休題>で、海外旅行や英語での失敗談を紹介しましょう。
Are you OK ?
日本人は、ちょっとした転倒や怪我のときに「大丈夫ですか?」と声をかけられると
ついなんとなく「大丈夫、大丈夫」と答える傾向がありますが、
どうやら欧米人の反応は違うようです。
これはロスアンゼルスのみやげ物屋のフロア-での経験ですが
転んだ方に「Are you OK ?」と気遣ったところ、すかさず「No I am not !」と切り返され
とても違和感と驚きを覚えたことがありました。やせ我慢は禁物です。
How are you ?
日本のある大学で、英語の試験のときのこと、解答に苦しんでいる学生に
気の毒がった試験官が「How are you ?」と尋ねると「I’m fine thank you, and you ?」と
英会話学校でのパタ-ンどおりの返事があって、試験官はビックリしたそうです。
語学には、テクニックより、実態・内容の裏打ちが大事だということです。
Bourbon on the rockS , double shotS !
英国ロンドンの下町なまりの英語を<コックニ->といいます。
オ-ストラリア英語がその典型で、paperは<パイパ->、dayは<ダイ>、
makeが<マイク>、cakeは<カイク>と発音され、このような“なまり”は
オ-ストラリア、ニュ-ジ-ランドだけではなく、アメリカ南部でもときどき耳にすることがあります。
オクラホマの南・ライトシテイでのことですが、レストラン隣のバ-から
アルコ-ルドリンクの注文を取りに来た女性の英語がこのなまりで
「オ-カイ?オ-カイ?」(OK? OK?)の連発です。
ちょっと、いたずら心が出て、「バ-ボンのオンザ・ロックでダブルだ。オ-カイ?」 と冷やかしたところ、
<オンザ・ロックス、ダボ-・ショッッツ>と自身の英語を複数形に修正して切り返されました。
くれぐれも、生半可な知識で他人を冷やかしてはいけませんね。
.............................................................................................................................

【第18回】飛騨の鰤(ブリ)街道
能登、越中から「飛騨ブリ」へ
冬の富山湾、とくに氷見の定置網で採れたブリは、能登ブリ・越中ブリと称し、
古くから京都、大阪で珍重されてきました。
いまでは新潟・佐渡の真野湾のものも「佐渡ブリ」として有名です。
越中ブリは、1670年代(寛文のころ)から、塩ブリとして飛騨の高山にも送られ
通称も「飛騨ブリ」と名前が変わります。
その後、さらに、標高1672mの野麦峠を越えて松本や木曽、伊那地方にも届けられます。
松本では、1尾の値段が浜値の4倍、コメ1俵(kg)相当(15,000円ほど)にもなっていたそうです。
鰤街道
越中から飛騨高山までのル-トは、まず、現在の高山本線沿いに南下するのですが、
途中、「猪谷」「今村峠」の間は、東西2本に分かれ、
東は越中東街道(神岡鉄道沿い)を運ばれました。
塩と同様、歩荷(ぼっか)に背負われて17日程の旅であったらしいのです。
「塩の道」からの想像なのですが、険しい<富山湾~糸魚川→塩の道→大町→松本>のル-トも
あったのではないでしょうか。ただ残念ながら、記録は見当たりません。
なお、小浜(福井)から京都へ夜行特急便で70km、鯖(サバ)を届ける若狭街道には、
江戸時代から「鯖街道」の愛称がありました。
各地の年取り魚
第16回のコラムでもお話ししましたが、日本各地には「年取り魚」があり
飛騨地方には、いまでも正月に塩ブリを「年取り魚」として食べる習慣があります。
兵庫県在勤の当時を思い出しましたが、年末になると多くの人々が
明石の「魚の棚」(小売市場)へ出かけて塩ブリを購入する姿が見られました。
塩ブリなので保存は利くし、いろいろな正月料理に使われます。
東京なら御徒町「アメ横」の歳末風景と同じでした。
NAFUの学生同士で自分たちの地元の食文化を共有する中で
新しいアイディアが出てくるかもしれませんね。
.............................................................................................................................

【特別版】新潟食料農業大学の開学に寄せて
いよいよ、「新潟食料農業大学」のスタ-トです。
意欲と好奇心に満ち溢れた若者たちが集い、この4月7日には新大学の第1回入学式が挙行されます。
いま、日本の「食」の市場は、年間80兆円、いずれは100兆円も目指せる巨大な経済セクターです。
消費者の期待に応えた「マ-ケット・イン」、農場と食卓を切れ目なくつなぐ「フ-ド・チェ-ン」、
くらしと地域に役立つ「実学」を学ぶのが最大の目標です。
建学の精神は、「自由」「多様」「創造」です。これらは、過去のしがらみにとらわれず
自己規律に基づく「自由」、他者の考えや行動を尊重する「多様」
好奇心に裏打ちされた「創造」を意味しています。
ここでは、習う・覚えるも大事ですが、積極的に質問し、提案する力を持った学生を育てていきます。
教員たちも、きっとそれに応え「面白いね、一緒に考えてみよう」と受けてくれることでしょう。
ここでの教育・研究を通じて、将来は、「食の総合大学」へ発展し、
地域における「知の拠点」としての役割を果たすことが期待されているのです。
メインキャンパスのある胎内市は、東に雄大な飯豊山脈を望み
山、森林、河川、海、田畑と、変化に富んで風光明媚な<花と緑の田園地域>です。
また、ビジネスを学ぶ新潟キャンパスは、大消費地にも近く
多くの食品産業が集積している好立地条件にあります。
恵まれたこの2キャンパスで、学生たちは生産、加工、輸送、販売、調理、サ-ビスを一連のものとして学び
消費と生産、都市と農村は別々ではない、対立するものでもないことを理解していきます。
300年近くも続く地域の市(三八市)にもグル-プで出店し、地域の人々からは歴史と暮らし、
文化・伝統などを勉強していきます。
消費者が求めるものを農場が生産し、都市が農村を支える<相互の理解と融合>を重んじる
教育・研究でありたいと考えています。
そして、施設も実習の場も理想的なものが整備されました。
学生たちの憩いの場「学生ラウンジ」の6階から日本海に沈む夕日を眺めるとき
日本という美しい国に住むことにみな感激を新たにすることでしょう。
「そもそも天下に道はない、人が歩いて道ができる」、
世界のフ-ド・チェ-ンをけん引するフロント・ランナ-の高等教育機関
「フ-ド・バレ-新潟」に向かって邁進します。
.............................................................................................................................

【第17回】食の東西②
お正月の雑煮 「お雑煮」の違いを一般的に
西では、①丸もち(茹でる)、②白味噌仕立て、③昆布ダシ、④具も賑やか、
これに対し東では、①角もち(焼く)、②醤油のすまし汁仕立て、
③ダシはかつおダシ、④具は比較的シンプルです。
しかし、関西や北陸、山陰にも、小豆汁や赤味噌仕立ての地域があり、もちの上に茹で小豆をトッピングする、
「もちが餡餅」など地域によって多様です。
最近では、面倒な丸もちが、加工しやすい角もちに取って代わられつつあるようにも見えます。
ダシの違いは何となく納得できます。北海道の昆布は、北前船で日本海を経由して北陸、関西に運ばれ、
かつおは、黒潮に乗って太平洋を上下する回遊特性が背景にあるからです。
ブリとカブの飯寿司
北陸の食文化に「かぶら寿司」(熟成ブリの切り身を塩漬けしたカブに挟み米麹で発酵させたもの)があります。魚、野菜と塩・米麹のナレ寿司は各地に見られますし、人々は、どこへ移り住んでも、
ふるさとの料理に近いものをと工夫をしますから、素材も、北海道では「鮭とキャベツ」、
秋田では「ハタハタとキャベツ」に代わります。
「麹」は、本来「糀」と書き、新潟市の古町にも「糀屋」の看板がありますね。
おでんと関東炊き
「おでん」にも、ダシ、タネ(種)、薬味には東西(中)の違いがあり
タネが、牛すじ、タコなどの関西風(大阪おでん)、魚の練りものや「ちくわぶ」を入れた関東風
それに、赤味噌ダレ、かつおダシと八丁味噌の甘めの名古屋おでんに分かれます。
東京の平河天満宮近くにある「おでんや」では、関東風、名古屋風、関西風と三種類の鍋があって
ダシ、タネ、薬味も異なるのですが、「ご当地おでん」を求めてにぎわいます。
農水省の機関誌「aff」には、このほか、「青森おでん」「静岡おでん」「姫路おでん」
「福岡おでん」「長崎おでん」も掲載されて、生姜を使う、削り節をかける、ゆず胡椒で食べる、
餃子巻、鶏の手羽先を入れるなどバラエテイに富んでいます。
私たちは、アジアモンス-ン地域の「照葉樹林文化圏」、「発酵食品文化圏」に暮らし、
そこでの食の共通性を持ちます。NAFUで、世界の食品と食文化について学びましょう。
.............................................................................................................................

【第16回】食の東西①
フォッサマグナ(中央地溝帯)の西縁が「糸魚川-静岡構造線」です。
食文化論では、「この西縁線あたりを境に西南日本と東北日本の食生活が分かれる」ともいいます。
そこで、これから2回にわたって、「食の東西の違い」を紹介していきます。
東のサケ、西のブリ
お正月用の塩魚を「年取り魚」といい、新潟、長野でも東西の違いが見られます。
下越・村上のサケ(塩引き鮭)は絶品ですが、佐渡あたりから西にはブリの立場が強くなるようです。
長野でも、東北信濃は「塩鮭」、松本、伊那、木曽地域では「塩ブリ」と好対照です。
しかし、最近は、加工、流通、貯蔵技術の変化やコ-ルドチェ-ンの発達、
食の国際化のなかで、境目は曖昧になっています。
NAFUでは、食の技術が食文化の変化に及ぼす影響も学びます。
牛と馬の違い、肉じゃがの違い
「北馬西牛」という言葉があります。輸送、荷役、耕作を牛、馬のどちらによるのかをいうものです。
奥州の馬は、平安時代から京都に献上され、また、交易の対象でもありました。
関東以北には広大な牧が展開して、馬の放牧、飼育にはこと欠かない一方、
西国ではその役割を牛が担っていたという説です。
明治になって、西洋の食習慣から牛肉を食べるようになったとき、関西では、廃牛が供給源として一般的になり、
牛の少ない関東・東北では、その地位を新規導入の豚が担うことになったのでしょう。
こうして、「肉じゃが」も、関西では「牛肉」、関東以北では「豚肉」がメインになって、
ところによっては、「すき焼き」の肉にも同じ傾向が見られます。
牛肉消費量を比較してみると、いまでも、西と東で大きな差があります。
神戸の食肉店では、牛肉に大きなスペ-スが与えられ、豚は肩身が狭いのです。
北海道・池田の「十勝ワイン」の製造は、地元の牛肉をもっと食べるようにと、
当時の町長が始めたと聞きます。
.............................................................................................................................

【第15回】塩の道‐千國街道と三州街道
地場調達から商品流通へ
近世になると、瀬戸内などの塩田の発達で、塩は日本海や太平洋回りの船で遠隔地へ輸送されるようになります。
湊に着いた塩は、その後は陸路で奥深い山国に向かいます。そのための専用交通路も整備されてきました。
南下する「北塩・下塩」
越後の糸魚川から信濃の松本に至る<塩の道>は「千國街道」で、
姫川沿いの険しい道では牛・人の背、やがて馬の背に代わります。
長い旅には牛が向いています。1頭で「通し」が効く、エサ<飼葉>がいらない牛は、
文字通りの<道草>で足りるからです。
小谷村には、牛と人が同居して泊まる「牛方宿」の地名も残っています。
登山では、「休憩する」ことを「一本立てる」といいますが、塩運びのボッカ(歩荷)が、
狭い山道で「背の重荷(50kg)に荷突棒を噛ませて立ったまま休む」というのが語源です。
もう一つの塩の道
信州に塩を届けるル-トには「千國街道」のほかに、
太平洋側の岡崎→足助→飯田→塩尻「三州街道」があります。
塩の旅の終点だから<塩「尻」>でしょうか。途中の足助では
三河「吉良」と「赤穂」の塩とがブレンドされ小俵に再包装されました(塩直し)。
輸送の利便化、味の調整・安定化、商品価値の向上は、昔からビジネスの基本だったのです。
吉良と赤穂、忠臣蔵の敵同士の塩がブレンドされる、面白いですね。
さて、上杉謙信の塩はどんなル-トで武田信玄に届いたか、推測してみてください。
塩を運ぶのは「にがり」を運ぶこと
純度の低い塩を運ぶことは、保存料「塩」と食品加工用の「にがり」を同時に運ぶことにもなります。
塩漬けにされた北陸の魚が信濃大町など山の町に届けられると、塩から魚を分離して販売し(塩イカ)、
濃塩水に含まれる「にがり」を使ってその地域の大豆を豆腐に製造することができます。
「塩イカの料理」が、遠く離れた北の大町と南の飯田、いずれでも名物なのは、
塩の道と関係が深いからでしょう。
.............................................................................................................................

【第14回】やはり気になる食料自給率 その②
数字から何を読み取るか
2食料自給率は農業生産、食生活、国の経済の総合力
豊かといわれ、食肉、乳製品、油脂類を多く食べる食生活では
その飼料・原料のトウモロコシ、大豆などを輸入に依存し、その消費ウエイトを大きくし、
自給率を低める方向に働きます。
農産物を輸入できる経済力が、食料自給率を下げることにもなるのです。
経済力が弱くて食料を輸入できない国々では、たとえ栄養不足になっても
国産の農産物・食料だけで生活せざるを得ません。その結果、食料自給率は100%に近くなります。
FAOが発表している「穀物自給率」では、ネパ-ル、バングラデシュが97%と
日本の穀物自給率28%をはるかに上回っています。
食料自給率が高かったころ
農水省の試算では、1960年のカロリ-ベ-ス総合食料自給率は79%でした。
高度経済成長が始まったばかりで食生活水準がまだ低かったときの数字です。
アメリカで「日本型の食生活が望ましい」と紹介されたのは1977年で、
日本の自給率は50%程度でした。(現在はカロリ-38%)
食生活も経済力も貧弱だった時代の食料自給率と比較してみても
これが幸せな姿なのかどうか考えさせられます。
最も望ましいのは、「国内生産力は高く、輸入もできる経済力もある」で、「高ければよい」ではなく、
健康的な食生活も考えつつ、国産、輸入・輸出と多角的に見ることです。
穀物消費量(一人当たり)
食肉、とくに飼料効率の悪い牛肉を多く消費する国、油脂を多く消費する国は、
その飼料・原料が穀物ですから、一人当たりの消費量も大きくなります。
アメリカが1066kg、中国が308kg、これに対し日本は246kg、牛肉を食べないインドは181kgですから、
こう見ると、人口が増えたら直ちに食料が足らなくなるともいえません。
食生活のあり方も関係していますから、100億人になろうとする世界人口も
工夫次第で養うことができる可能性があります。
(牛肉は、豚肉の2倍、鶏肉の3倍近くの穀物が必要です)
食料自給「力」
最近では、「食料自給力」という表現も「食料農業農村基本計画」などでは使われています。
「耕作放棄地の回復、河川敷やゴルフ場の農場化などで穀物やイモ類などカロリ-の高いものを生産する、
さらには、一つの農地を表・裏2回使う二毛作を盛んにして生産量を増やすことで
どの程度の栄養水準を賄えるか」という安全保障上の計算です。
(2013年のFAOの調査では、一人一日当たりのカロリ-摂取量は、豪州が3768Kcal、
アメリカが3682Kcalに対し、日本は1800~2000Kcalとなっています)
このように、<食料自給率>の数字やレベルには、それぞれの意味や意義があるので、
そこを十分理解して将来の農業生産や食生活を考えていくことが大事です。
NAFUでは国内外の農業・食料を取り巻く自給率や経済の流れを
「食・農・ビジネス」の幅広い視点からとらえる力を身に付けていきます。
.............................................................................................................................

【第13回】やはり気になる食料自給率 その①
いろいろなタイプの自給率
2回にわたって、食料自給率を考えます。
<国内生産 ÷ 国内消費 x 100=%>が計算式ですが、
分子の「国内生産」には輸出に向けられる分も含まれています。
品目別自給率
個別の農産物ごとに重量で国内生産比率を計算する分かりやすいものです。
この場合、牛肉、豚肉、鶏肉、乳製品などの畜産物では、
飼料(エサ)が輸入であっても、最終製品が国産なら国内自給にカウントされ
自給率は高くなります。
カロリーベース総合食料自給率
この数字の見方には注意を要します。畜産では、輸入飼料穀物を多く使うので、
畜産物がいくら国産でも、原料に当たる飼料が輸入だと、
その分はカロリ-換算で差し引かれます。
豚肉1kgを生産するためには輸入のトウモロコシ7kg、牛肉1kgでは11kgが必要で、
畜産物の国内生産が増加するほどカロリ-ベ-スの自給率は下がってしまうという弱点を抱えています。
また、野菜や果実には、カロリ-が少ししかないので、自給率向上には貢献できません。
「カロリ-ベ-ス自給率」は、昭和40年の73%から、平成28年の38%になりました。
数字には、食生活が豊かになるのに従って下がったという背景があることも考えましょう。
海外では、あまり使われない自給率です。
生産額ベ-ス総合食料自給率
国内生産の総額と輸入の総額を比較して計算します。
しかし、こちらも「為替レ-トの変動」などで換算数字が動くことがあります。
小さな変化だけを見て、過剰な反応をしない方がよいかも知れません。
(昭和40年86%→平成28年68%)
飼料自給率
家畜は草で育てるのが生理上は望ましいのですが、国土の狭い日本では
食生活の向上テンポに草地・飼料畑の規模が追いつかないので、輸入の飼料に大きく依存しています。
牧草と穀物では飼養効率が異なりますので、
可消化養分総量(TDN)に換算して国産と輸入を比べて計算されます。
これは、食肉、乳製品などの「真の」自給力を示しているといっても差し支えないでしょう。
(昭和40年55%→平成28年27%)
穀物自給率
輸入が途絶える・制約される、経済的にも買えないときには、
国内生産だけで食生活の水準を維持することになるので、
カロリ-の基本である穀物(米、麦、大豆)の自給率があまりにも低いことが心配です。
先進国では、常日頃から穀物自給率を高く維持する政策、例えば、輸出を予備の供給源とし、
いざのときには国内に回すことも可能な政策を採用しています。
豪州、カナダ、アメリカなどの広大な農地面積の国々は当然100%を超え、
フランスは173%、ドイツ、英国、ロシア、中国もほぼ100%です。
これに比べて、日本の数字28%は、農地面積だけでなく、
農業政策の違いが数字に表れているような気がします。
(昭和40年62%→平成28年28%、米などの主要食用穀物では59%)
*次回は「やはり気になる食料自給率 その② 数字から何を読み取るか」です。(渡辺 こうめい)
.............................................................................................................................

【第12回】有機農業について考える
「有機農業」の始まり
農業生産を高めるために有機物を肥料として投入するのは江戸時代からごく自然のことでしたが、
科学的、哲学的に系統だてたのは、一楽照雄さんで、1971年ごろのことでした。
「経済の領域を超えた価値を有する、豊かな地力と多様な生態系に支えられた土壌から生み出される
本来あるべき農業のあり方」と提唱したのです。
有機農業推進法
10年ほど前にできたこの法律では、有機農業の「定義」を
<化学的に合成された肥料、農薬を使用しない、遺伝子組み換え技術を利用しないことを基本に、
農業生産から環境への負荷をできる限り低減した農業>といっています。
これを規格化した有機JASには、「有機農産物」と「特別栽培農産物」の2つの基準があります。
なぜ有機農業なのか
農業生産の母体は「土壌」です。気の遠くなるような長い時間をかけて動植物の遺体(有機物)が
蓄積されていまの豊かな土壌があるのですが、雨の多い日本では、
微粒子や養分が洗い出されてしまう弱点を持っています。
土から抜け出したものを直接に補う必要が出てきます。
ブルガリアのヨ-グルトも、かつては海で、隆起した草原の土・草には魚類や海藻由来の養分が含まれ、
乳牛が育つと聞いたことはないですか。
なにを目指しているのか
有機農業を研究する方々は、①安全・良質、②自然・環境、③地力・地域、④生物多様性、
⑤生産者・消費者の連携、⑥農の価値などといいます。
自分の経験でも、長野県安曇野の自宅のすぐ前の畑(水田)では、
加工用のトマトを「無農薬」「無肥料」で3年連作するのを見ましたが、順調のようでした。
そして、生産方法にこだわる消費者の方々と連携し、商品向け収穫の後には、
最後に残ったトマトをみな引き受けていました。
家庭でピュレ-などにしてビンに詰め、冷凍・冷蔵保管して料理に使うのだそうです。
注意することは どんな成分がどのくらい足らないのかの「土壌分析」から始めます。
また、有機物は、「発酵すれば益、腐敗をすれば害」ですから、たい肥づくりには慎重を要します。
加えて大事なことは「濃度」と「必要量」で、<過ぎたるは及ばざるがごとし>です。
NAFUの稲作実習でも、一般的な「慣行栽培」と「有機農法による栽培」を体験します。
*次回は「やはり気になる食料自給率 その①いろいろなタイプの自給率」です。(渡辺 こうめい)
.............................................................................................................................

【第11回】アメリカ映画に見る食料・農業
「閑話休題」第6回の学長コラム(GMO)で映画「キングコ-ン」を取り上げましたが、
それに因んで、アメリカ映画に登場する食料・農業の姿を取り上げたいと思います。
怒りの葡萄(1940年 ヘンリー・フォンダ主演)
1920年代の経済不況、農業不況(農産物価格低落、砂嵐災害)に見舞われた中西部から
西海岸へ移住の旅ですが、砂嵐(Dust Bowl)は、単なる自然災害でなく、
背景には、農業の機械化・集約大規模化、資本主義化があります。
トラクタ-の発明・普及は、抜本的に生産性を向上させましたが、
同時に、農地の過度深耕、堆肥など栄養分不足、土壌流出と農村地域での過剰就業を招きました。
実際にも、アメリカのミシシッピ川もテキサス・オクラホマの「レッドリバ-」も、
日本とは違って赤く濁っています。機械化、技術化には、損なわれるマイナス点を補う視点が大事です。
機械化と農業、戦争との関係は、「トラクタ-の世界史」(藤原辰史)が参考になります。
エデンの東(1955年 ジェームス・デイーン主演)
1917年当時のカリフォルニア・サリナスを舞台とし、主題は、父と息子、
兄と弟の人間関係ですが、父親の栽培するレタスが重要な役割を果たしています。
父親に疎外されていると感じた次男のキャルは、自らの存在価値を認めさせようと一攫千金を夢見て、
カリフォルニアのレタスを冷凍保存し、貨車で東部に輸送しますが、
途中での雪崩により通行不能、腐らせて大損をします。
コ-ルド・チェ-ンが整備されていないころの生鮮食料品の流通とマ-ケットの関係を通し、
農産物は、ただ作ればよいのではなく、届いて・使われてこそが最終使命であると分かります。
目撃者(1985年 ハリソン・フォード主演)
アメリカ社会、とくに農村の多様性を知ることができる傑作だと思います。
正式名は、たぶん「刑事ジョンブックの目撃者」(Witness)で、
空港トイレで殺人犯を目撃したア-ミッシュの少年と母親を守るため、
ア-ミッシの村に入る刑事、追いかける犯人は身内ともいえる警察官であることから話は複雑になります。
この物語では、16世紀のオランダ、スイスに発し、
迫害から逃れてアメリカに移住してきたドイツ系住民の伝統的な生活、
石油由来のものは使わない、有機農法での農業生産、すべてを住民共同で行う生き方が見事に描かれます。
ペンシルバニア州ランカスタ-地域などが有名ですが、いまでも各地にア-ミッシュの村があります。
自動車道でゆうゆうと1頭立ての馬車を操り、衣服も木綿、麻などの天然繊維、
色は白と黒、ボタンは貝というスタイル、農場は、人力、馬力が中心で動かす姿を見たとき、
人間の生き方を拘束しないアメリカの多様性を強く感じました。
英語では、<It’s OK,Not me!>と表現します。
他にも、農業更生局に差し押えられたアイオアの農場の競売を地域コミュニテイ全体で阻止する映画
「カントリー」(1984年 ジェシカ・ラング主演)も印象深いものがありました。
映画を入り口に食料・農業分野における問題を考えてみるのも良いきっかけになります。
*次回は、「有機農業について考える」です。
(渡辺こうめい)